品川恭子."八ツ手"の染め帯と山下八百子.本場黄八丈..、これで良いかな?
 "着物と帯のあわせ"...、山下八百子さんの本場黄八丈と品川恭子さんの染め帯との"着物と帯のあわせ"。
"着物と帯のあわせ"...、山下八百子さんの本場黄八丈と品川恭子さんの染め帯との"着物と帯のあわせ"。さて..、この"あわせ"なんですが、単純に、着物と帯のグレイド的な視点で"あわせ"ている訳ではありません。
そもそも、品川恭子さんのこの染め帯...、"八ツ手"の染め帯をどんな着物に、どんなTPOとして楽しめるのかな、と言った感じで考えていたのですが、眺めているとちょっと他にはない存在感が感じられるようになったのです。
塩瀬素材の生地に"八ツ手"の葉が染め描かれています。
それも、枯れ朽ちて、虫喰い葉となった八ツ手です。
加賀友禅に特徴的に染め描かれている虫喰い葉ではなくて、本当に枯れ朽ちている姿が染め描かれています。
この"八ツ手"なんですが、着物とか帯の図案そのもの以上に、実に巧く染め描かれています。
"ろうけつ染め"の濃淡を巧み使うことで、枯れ朽ちた雰囲気が見事に表現されているんですね..。
こうした作風なんですが、実際にみて知ってしまうと、当たり前の様に、また、ごく自然に眼に馴染んでしまいがちではあるのですが....、"染め描く"ことで、"ろうけつ"の濃淡でこうした雰囲気を表現すると言うのは、あまりみたことはありません。
品川恭子と言う染色家の絵画的センスから生まれたものだと思います。
さて..、こうした枯れ朽ちた虫喰い葉の染め帯なるものは、当たり前なものとして捉えるならば、"趣味趣向に興じたもの"となると思いますが、この品川恭子さんの"八ツ手"から感じる空気感は...、違うのです。
この枯れ朽ちた"八ツ手"なんですが、とても綺麗な感じが伝わって来るのです。虫に喰われ、枯れ朽ちた葉が染め描かれているにも関わらず、とても綺麗な感じ...、清潔感をも感じられるのです。
ただ趣味趣向の染め帯...、ろうけつ染めの帯...、"ちょっと洒落ていますよ"ではないのです。
だからと言って、この枯れ朽ちた虫喰い葉の染め帯が、凛とした手描き友禅の染め帯如き礼装感を伝えるかと言うと..、また、違うのです。そもそも、枯れ朽ちていて礼装と言う訳にはいかない筈ですね。
この"八ツ手"は、染色家.品川恭子さんの美意識から生まれた孤高の存在感があるのです。
こうした存在感をどう使うか..、如何に楽しむかは..、着物との"あわせ"の楽しさに繋がるじゃないかと思います。
 そこで、山下八百子さんの本場黄八丈...、黄八丈と言うより"鳶"の匂いのある黄八丈を"あわせ"のお着物として取り上げてみました。
そこで、山下八百子さんの本場黄八丈...、黄八丈と言うより"鳶"の匂いのある黄八丈を"あわせ"のお着物として取り上げてみました。この黄八丈は、紬織物でなりながら、通常、紬織物には感じられない特別な感じが伝わってくるのです。
紬織物にありがちな、素朴さとか普段着的な雰囲気はまるでありません。色も...、細かく綾織として織られた多彩色が、独特の色印象をつくっています。おおざっぱに言ってしまえば、鳶色は鳶色なんですが、眼にしている色は、"鳶色"と言う言葉以上の美しさと深さを感じるのです。
この着物は、光の加減や帯とのバランスによって、色の加減や織の表情が移り変わるのです。精緻な綾織と植物からつくられた色が相俟った特別の感じなんだとと思います。
普段着的な空気感はありません。また、いかに綺麗な織物といっても、礼を意識したお着物となる訳ではありません。
"あわせ"のConceptとしては、着物や帯...、それぞれから伝わってくる存在感を"あわせ"てみてみたのです。
色艶や素材感からすると、こうした"あわせ"よりも、もっと馴染む"あわせ"はあるかと思います。
この"八ツ手"の地色や雰囲気から想うと、薄灰色系の江戸小紋とか落ち着いた地色の文様散らしの小紋などに"あわせ"ても違和感なく馴染む筈です。それは違和感や不自然さがない"姿かたち"のバランスを適わせた"あわせ"に止まります。
品川恭子さんの"八ツ手"の染め帯も、山下八百子さんの本場黄八丈も、特別な存在感を持っている...、そして、不自然さなく馴染むのでしたら、着物や帯、それぞれから感じるもの...、メンタルな視点で"着物と帯のあわせ"を探し楽しんでみるのも良いと思います。
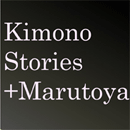
 "着物と帯のあわせのCocept"..、今回は"普段遣いのあわせを楽しむ"と言うテーマでお話を進めてみたいと思います。
"着物と帯のあわせのCocept"..、今回は"普段遣いのあわせを楽しむ"と言うテーマでお話を進めてみたいと思います。 こうした本場結城紬だけで、"普段着的な装い"を演出することも出来ると思います。
こうした本場結城紬だけで、"普段着的な装い"を演出することも出来ると思います。 先日、京都.東福寺の紅葉を堪能して参りました。
先日、京都.東福寺の紅葉を堪能して参りました。 こちらの写真画像は、通天橋の傍らのお庭で撮影しました。
こちらの写真画像は、通天橋の傍らのお庭で撮影しました。 龍吟庵のお庭は、その方丈を囲んで..、東.西.南にそれぞれ枯山水が配されています。
龍吟庵のお庭は、その方丈を囲んで..、東.西.南にそれぞれ枯山水が配されています。 日曜日、名古屋はとても秋晴れで、紅葉日和の一日でした。
日曜日、名古屋はとても秋晴れで、紅葉日和の一日でした。 辻が花/創作家.森健持氏が手掛けた絵羽織。
辻が花/創作家.森健持氏が手掛けた絵羽織。 以前に、"着物と帯のあわせのCocept"のお話をしたと思います。
以前に、"着物と帯のあわせのCocept"のお話をしたと思います。 添田敏子さんの型絵染めは、まるで近代西洋絵画の如き強い迫力があります。
添田敏子さんの型絵染めは、まるで近代西洋絵画の如き強い迫力があります。 前回お話をさせて頂いた"あわせ"...、「御所解の染め帯と志毛引き染めお着物」に引き続き、今回も「小紋と染め帯」の"あわせ"をご紹介してみたいと思います。
前回お話をさせて頂いた"あわせ"...、「御所解の染め帯と志毛引き染めお着物」に引き続き、今回も「小紋と染め帯」の"あわせ"をご紹介してみたいと思います。 TPOとしては、礼装が求められる場所や席"未満"...、余所行き"以上"...、と言うところです。
TPOとしては、礼装が求められる場所や席"未満"...、余所行き"以上"...、と言うところです。 つい先日、お店の近くに咲いていたお花です。
つい先日、お店の近くに咲いていたお花です。 ちょっとお着物のお話から離れて、久しぶりに音楽の話題をほんの少しだけ...
ちょっとお着物のお話から離れて、久しぶりに音楽の話題をほんの少しだけ... 勝山健史氏が制作した西陣織九寸名古屋帯。
勝山健史氏が制作した西陣織九寸名古屋帯。